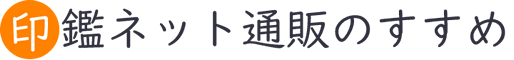自治会で使っている集会所や駐車場の土地があるけれど、昔の役員の名前で登記されていて変更できなくて困っていることなどありませんか?
他にも、自治会長が変わるたびに会計を管理している通帳の名義を変更しなければならなくて不便ということもありますよね。
自治会を法人化することで、土地や建物を登記できますし、毎年通帳の名前を変更する必要もなくなります。
自治会の法人化には、認可地縁団体やNPO法人がありますが、ここでは認可地縁団体についてお伝えします。

法人化(認可地縁団体)の法的根拠
以前の自治会は、権利義務を持たないいわゆる「無能力者」でした。
そのため、自治会組織の土地であっても、自治会名で不動産登記することはできませんでした。
そこで、平成3年4月に地方自治法が一部改正され、法人化することができるようになったんですね。
その根拠法令は次のとおりです。
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
引用元:地方自治法
法人化された自治会は「認可地縁団体」と呼ばれ、認可地縁団体に関する法的根拠は地方自治法第260条の2から第260条の40までに規定されています。

法人化するメリット
- 不動産登記できるようになる
- 会計用通帳の名義変更する必要がなくなる
- 代表者の責任を軽減できる
- 補助金などが受けやすくなる
メリットとしては名義の問題ですね。
不動産登記できるようになる
以前は、当時の自治会長や役員たちが共有で不動産の所有者として登記されていました。
これの何が問題かというと、登記名義人が亡くなれば相続が発生しますから、本来であればその都度所有権移転登記をしなければなりませんでした。
共有名義ともなれば、相続が発生する回数も増えますし、相続人は他市町村へ引っ越している可能性もあります。
最近では、空き家対策としても問題になっていて、昔の共有名義の物件を取り壊したり、メンテナンスしたくても所有者でないために手が出せないなどの問題も起こっていますよね。
法人として登記することができるようになると、自治会長が変わっても登記しなおす必要もありませんから、その都度自治会内で相談しながら不動産を管理できるようになります。
他にも、自治会が所有していることがわかるので、固定資産税の減免申請も通りやすくなるはずです。
会計用通帳の名義変更する必要がなくなる
認可を受ければ、法人格を持つことができますから、通帳も法人として作成することができるため、毎年通帳の名義を変更する必要がなくなります。
法人化前の自治会だと、「○○自治会 会計○○ ○○」という名義になっていて、自治会長や会計担当者が変わるたびに銀行へ行って、通帳の名義を変更していたと思います。
サークルなどで通帳を作っていた、いわゆる「任意団体」という扱いでしたよね。
認可地縁団体であれ、NPO法人であれ法人化できれば銀行口座も法人として開設することができます。
代表者の責任を軽減できる
法人化前の自治会の場合、最終的な責任は個人が負うことになります。
それでは、自治会長をやってやろうという人は少ないでしょう。
法人化することにより、責任の所在が個人から法人へと移りますから、自治会長個人の責任を軽減することにつながります。
補助金などが受けやすくなる
自治会で行う事業の内容によっては、市町村からの補助金を受けることができるものがあります。
法人化することで対外的な信用度は上がりますから、補助金申請が通りやすくなり、自治会で行う事業についてもスムーズに進めることができるはずです。
法人化するデメリット
- 認可手続きが必要
- 法人化後は地方自治法の制約を受ける
- 法人税などの対象になることもある
地縁団体として法人化することは、メリットだけではありません。
法人化することで信用を得るわけですから、次のような制約を受けることもあります。
認可手続きが必要
認可地縁団体となるためには、市町村長の認可が必要です。
そのためには、要件を満たす団体が、各種の書類をそろえて提出する必要があります。
法人化する際の自治会長さんは、何度も市役所へ足を運ぶなど、時間と手間が必要になります。
法人化後は地方自治法の制約を受ける
先ほどもお伝えしたとおり、認可地縁団体は地方自治法第260条の2から第260条の40までに規定されています。
例えば、「総会を年に1回開催しなければならない」とか「最新の財産目録を事務所におく」など、書類ごとも多くなります。
さらに、規約にない活動をするためには総会の議決が必要になるなど、役所のようになってしまい、フットワークに欠ける部分が出てきます。
法人税などの対象になることもある
認可地縁団体は、法人税法上は公益法人とみなされます。
消費税についても一般社団法人などと同様の扱いを受けます。
そのため、収益事業を行っている場合には納税の必要性がありますから、所轄税務署などに相談しておきましょう。
さらに、法人を設立したということで各種法人設立届を提出する必要があります。
自治会を法人化する手続き
自治会の認可地縁団体化は、市町村の担当部署に相談しながら進めていきます。
前提として、「すでに不動産を持っている」か「近いうちに不動産を取得する予定」の自治会である必要があります。
申請に関しては、市町村のホームページに詳しく情報を提供してくれているところもあります。
参考市町村ページの例
認可申請できる前提条件
- その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
- その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
- その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
- 規約を定めていること。
形式上の自治会ではなく、実際に継続して自治会活動を行っていることと、そしての活動内容についてルール化(規約)している必要があるということですね。
そして、自治会はどのエリアが対象なのかをハッキリさせ、そのエリア内の住民は個人単位で誰でも入れる必要があるということです。

認可申請準備
まずは自治会内に認可地縁団体となることを説明して周知する必要があります。
理解が得られれば準備を進めます。
- 市役所と相談しながら規約を作成
- 規約の承認と認可申請することの最終決議
一般的な規約のひな型などを見せてもらいながら、規約の案を作っていきます。
その際に、法人化することによる注意点なども聞いておくと良いと思います。
規約の案ができれば、内容について自治会員の承認を得ましょう。
自治会内で法人化に向けて動くことが決まれば、認可申請に必要な書類を作成していきます。
認可申請書類の提出
認可申請に必要な書類としては、一般的に次のようなものがあります。
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決した議事録
- 構成員の名簿
- 区域を示す図面
- 保有資産目録または保有予定資産目録
- 前年度と当年度の事業報告書
- 役員就任承諾書
※ 参照「地方自治法施行規則第18条」
具体的な提出書類の内容や様式については、申請する市町村役場で確認するようにしてください。
ホームページなどでダウンロードできるようになっていることが多いです。
認可後に告示されて法人化が完了
申請書類を整えて、市町村役場の担当部署に書類を提出すると、市町村の審査に入ります。
無事認可されれば、市町村長により告示されます。(地方自治法第260条の2第10項、施行規則第19条)
告示後は認可地縁団体としての権利と義務が発生することになります。
認可地縁団体の印鑑登録
法人化したあとに、印鑑登録申請をする必要があります。
これは、株式会社などでも同じですが、法人としての実印を登録しているのと同じです。
印鑑登録するための法人としての印鑑を作成しておきましょう。
実印として登録する印鑑以外にも、角印や銀行印も合わせて作っておくと良いです。
自治会の実印として登録できない印鑑については、各市町村の条例を確認してください。
登録できない印鑑の例
- ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
- 一辺の長さ 8 ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ 30 ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 磨滅又は損傷しているもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- その他市長が不適当と認めるもの
不動産登記申請をして完了
- 認可地縁団体の印鑑登録証明書
- 告示事項証明書
地縁自治体としての認可がおりたあと、無事印鑑登録が完了したら、上記2つの証明書を入手します。
どちらも市町村役場で申請することで取得できます。(1通300円程度)
これによって、法人格を持っていることと、代表者の印鑑を確認することができるようになります。
この2つの書類を添付して、自治会が使用している土地や建物を法人化した自治会名で登記することができるようになります。